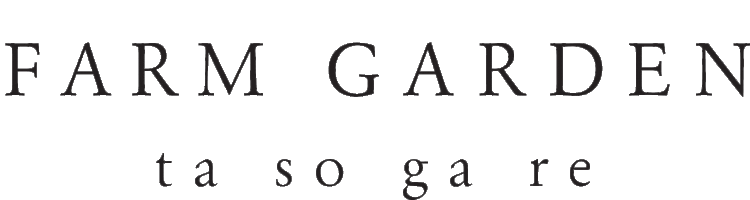たそがれ野育園OBで秋田市上北手にていのちやすらぎファームを運営している進藤先生のご自宅にて「鳥のいのちをいただくワークショップ」に高嶺家と参加させていただきました。
お誘いできなかった皆様には申し訳ありませんが、ご報告いたします。
⚫︎もしかしたら閲覧注意になるかもしれませんが、ご了承ください。
進藤先生はたそがれ野育園初年度生として不耕起栽培の稲作りを学びにきてくださり、その後、ご自宅裏の水田にて不耕起栽培を実践しながら、いのちやすらぎファームとしてお仲間とともに水田での稲作ほか、畑での豆作りや麦作りのほか、比内地鶏の平飼いを行っております。
(現役時代は秋田大学医学部の臨床医学療法士、そして現在は秋田立憲ネットの代表をされていることもあり、ご存知の方も多いかと思います)
今回お声がけいただいて、生きた鳥を一羽ずついただくまでの工程を手ほどきいただきました。


慣れた手つきの進藤先生の手ほどきを受け、ただっさんが一羽のいのちを。
僕は抱えた鳥を手にした時に、娘から「お父さんやめて!」の一声がかかり、進藤さんにあやめていただくことになりました。


10分ほどの血抜きのあと85度のお湯に浸すと、
驚くように鳥の羽を抜くことができ、ここから先は子どもたちも手をかけることができるようでした。

一羽から2本しかいただくことのできない手羽の骨を脱臼させ、皮を断ち、肉と骨を分け、



次に足を落とし、5本の腱を抜き取り、二枚のモモ肉となりました。
中から薄皮ほどの胎内卵と砂肝、心臓と肝臓と食べられる部位を解体し、肉と骨とに分けることができました。
2時間ほどのオペだったでしょうか。進藤先生の「◯◯骨のここにメスを」という指導のもと淡々とこなした鳥のいのちをいただく時間は

その後ズシンと重い疲労となって僕の体に残りました。
決して楽しいと言えるような時間ではありませんが、食を考える上で貴重な経験をこどもたちとともにできたことに感謝し、
そして何よりこのいのちに感謝し、口にしたいと思います。

持ち帰った丸鷄をどういただくか考える暇もなく、こんな日は「だまこ鍋」で決まり!我が家では収穫祭といえばだまこを食べます。ひなたが野育園で育てたこしひかりを自ら炊いて、妹と弟でそれを潰しだまこもちをつくります。




ようじろうは待ちきれずにだまこを頬張り、さっきまで生きていた鳥の骨からはスープをいただくことに。ダシ取り当番は三女に。





いのちの重みを家族一身で感じ、いただきます。おいしいねっ
ていただきました。